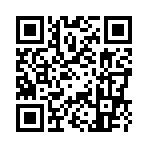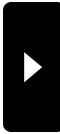2011年01月27日
stop the clocks Ⅱ


Posted by macoto at 19:16│Comments(4)
│建築
この記事へのコメント
時の雫から
ずっと辿ってくると
木造の建物のほうに親近を覚えます
この建物などは相当年数を経ているのでしょうが
風のそよぎとか匂いとか湿気とか
いろんなんものを内部に吸い込んでいる
からでしょうか
破壊しがたい
ずっと辿ってくると
木造の建物のほうに親近を覚えます
この建物などは相当年数を経ているのでしょうが
風のそよぎとか匂いとか湿気とか
いろんなんものを内部に吸い込んでいる
からでしょうか
破壊しがたい
Posted by ボードレリアン at 2011年01月30日 18:34
〓 ボードレリアン さんへ
いつもアクセスありがとうございます。
丁度、昭和の初期か大正後半の建物だと思います。
当時のシンメトリーな外観、縦長の上下窓のデザインが流行りだったのでしょう。
今の建築と違って、工業製品がほとんど無く現場での手作りがとても暖かさを感じますね。
でも不思議な事に、人の出入りが建物から無くなると、急に建物は傷んで来るのです。
もう二度とこんな建物は建つ事は無いので、とても愛おしくシャッターを切っています。
いつもアクセスありがとうございます。
丁度、昭和の初期か大正後半の建物だと思います。
当時のシンメトリーな外観、縦長の上下窓のデザインが流行りだったのでしょう。
今の建築と違って、工業製品がほとんど無く現場での手作りがとても暖かさを感じますね。
でも不思議な事に、人の出入りが建物から無くなると、急に建物は傷んで来るのです。
もう二度とこんな建物は建つ事は無いので、とても愛おしくシャッターを切っています。
Posted by macoto at 2011年01月31日 18:02
at 2011年01月31日 18:02
 at 2011年01月31日 18:02
at 2011年01月31日 18:02昭和初期か大正後半というとほぼ100年ですね。
先日大手ゼネコンの高層ビルの解体技術の
ニュース記事を読みましたが、その寿命の短い
ことに驚きました。それに反して、木造建築は
条件が良ければ100年くらいは保つと聞きました。
工業製品がなくて現場での手作り、そういう暖かさは
確かにありますね。
東京の場合、本郷、千駄木、湯島あたりの下町に近い
地域の昔の家並はもうほとんど見られないそうです。
昨年末に神田から有楽町までずっと歩きましたが、
友人はもう駄目だって言ってましたね。
東京駅もすっかり変わってしまった。
先日大手ゼネコンの高層ビルの解体技術の
ニュース記事を読みましたが、その寿命の短い
ことに驚きました。それに反して、木造建築は
条件が良ければ100年くらいは保つと聞きました。
工業製品がなくて現場での手作り、そういう暖かさは
確かにありますね。
東京の場合、本郷、千駄木、湯島あたりの下町に近い
地域の昔の家並はもうほとんど見られないそうです。
昨年末に神田から有楽町までずっと歩きましたが、
友人はもう駄目だって言ってましたね。
東京駅もすっかり変わってしまった。
Posted by ボードレリアン at 2011年02月01日 23:53
木造建築では日本の大工技術は素晴らしいものがあります。
安土桃山時代には高層木造建築の技術がお城や五重の塔などに生かされ
1000年風雪や地震に耐える構造が今も受け継がれています。
でも、今の時代建築は、経済優先の工業製品になってしまいそうで、
一部の改修以外では、ほとんどユニット工法などになっています。
命を守る建築に、どうしてもコスト概念を優先させてしまうこの不況をどうか
終息させてほしいと願っております。
安土桃山時代には高層木造建築の技術がお城や五重の塔などに生かされ
1000年風雪や地震に耐える構造が今も受け継がれています。
でも、今の時代建築は、経済優先の工業製品になってしまいそうで、
一部の改修以外では、ほとんどユニット工法などになっています。
命を守る建築に、どうしてもコスト概念を優先させてしまうこの不況をどうか
終息させてほしいと願っております。
Posted by macoto at 2011年02月02日 18:39